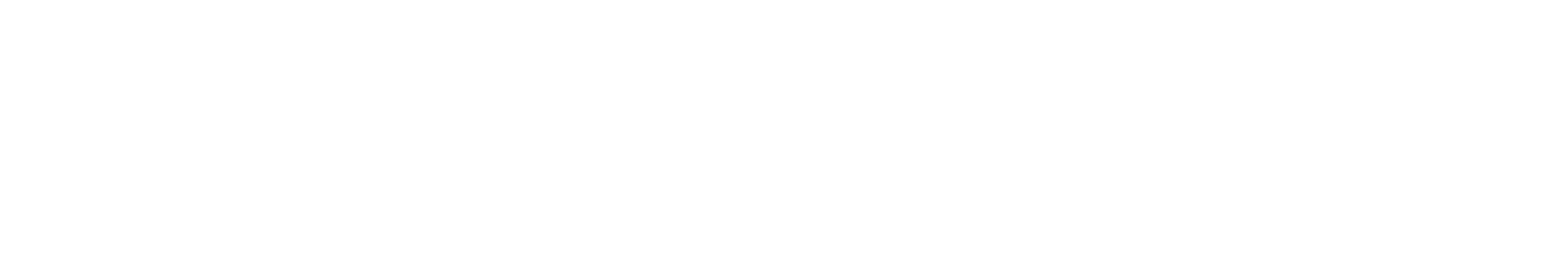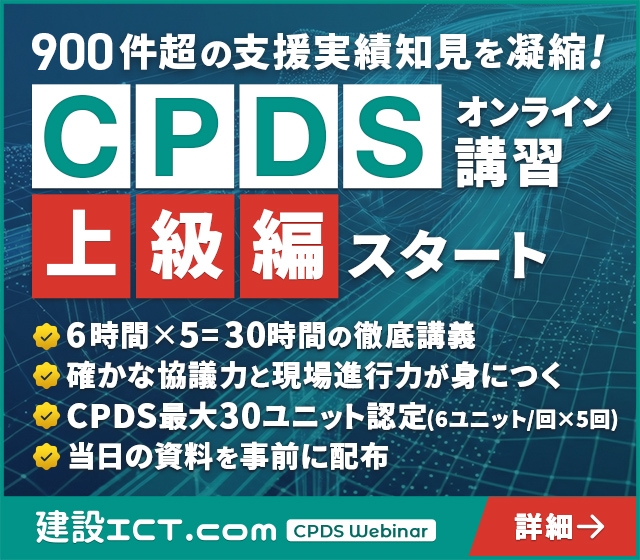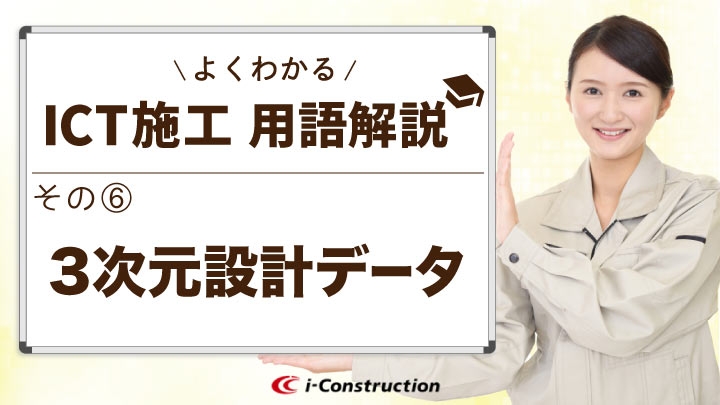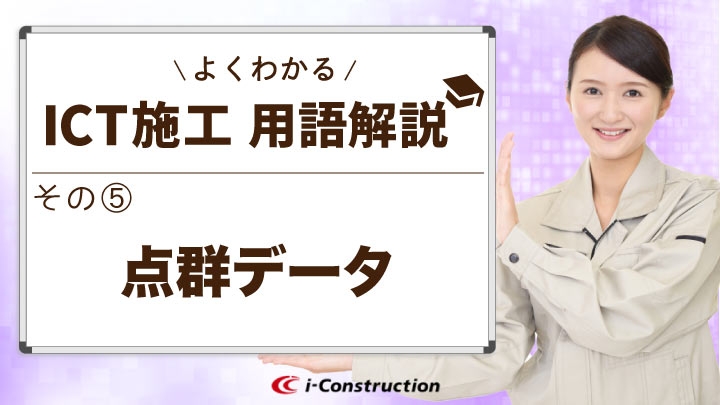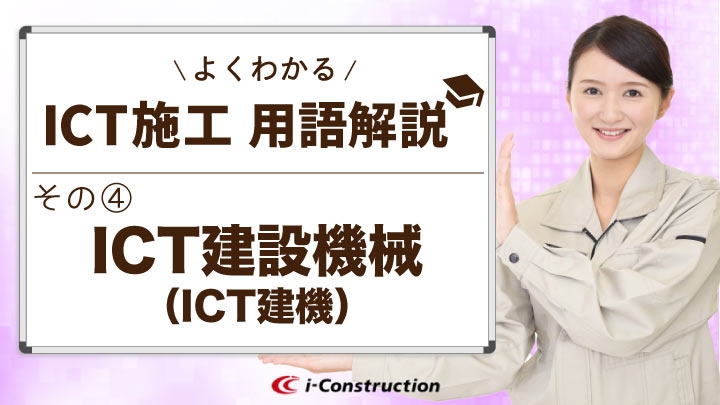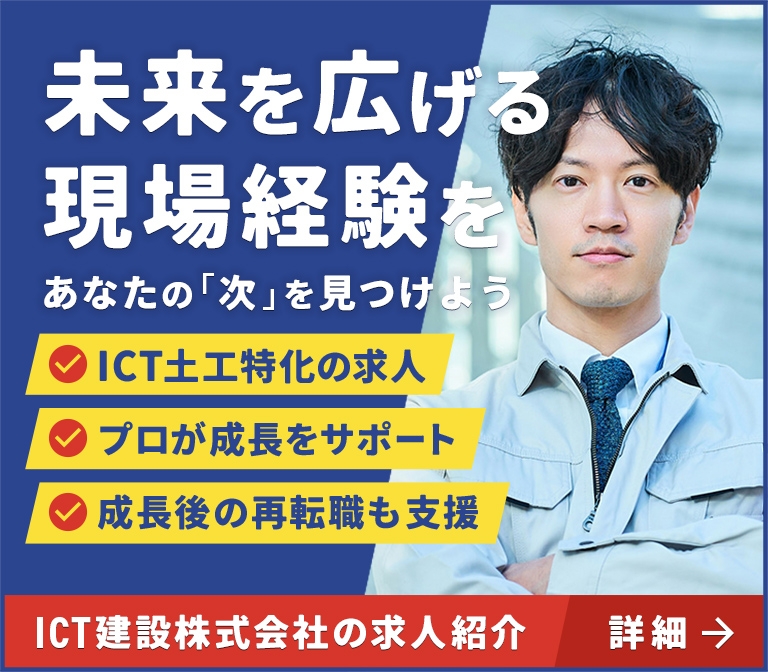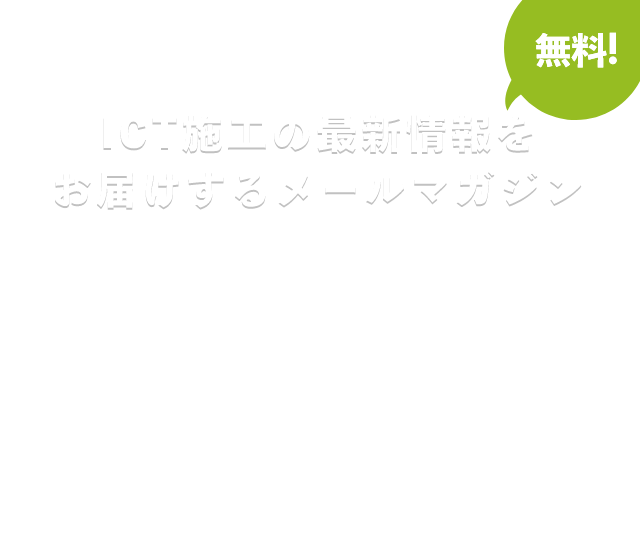国土交通省は、令和7年2月25日に「第13回 BIM/CIM推進委員会」、2月26日に「第20回 ICT導入評議会」を開催しました。
各会議では令和6年度の取組みを振り返りながら、新年度に向けたBIM/CIM・ICT施工の取組みの進め方について議論が行われました。
今回のコラムでは、その中でも特にわたしたちが注目したトピックについてポイントをまとめて行きたいと思います。
▼第13回 BIM/CIM推進委員会
https://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000147.html
▼第20回 ICT導入評議会
https://www.mlit.go.jp/tec/constplan/sosei_constplan_tk_000052.html
ICT施工の取組み推進の動き
ICT施工 StageⅡへの移行
国土交通省はICT施工の取組みを3つのステージに分け、段階的に進めていく方針を打ち出しています。
令和6年からは「ICTを活用することで建設現場で得られる様々な情報を見える化する」ことを狙う「StageⅡへの移行」が始まりました。
「データ活用による現場マネジメントに関する実施要領(案)」も出されており、その中では以下の4項目のいずれかを実施する工事がStageⅡの対象とされています。
- 施工段取りの最適化
- ボトルネック把握・改善
- 進捗状況等把握による予実管理
- その他(注意喚起・教育等)

令和6年度は国土交通省直轄のStageⅡ試行工事が15件実施され、省人化について一定の効果が確認されています。
ICT施工の原則化
「ICT施工の原則化への移行が始まること」もトピックのひとつです。
令和7年度にはついに、土木・河川浚渫についてICT活用工事が原則化されます。
それに伴い、以下のような変更点があるようです。
| 現状 | 令和7年度 | |
|---|---|---|
| 発注方式 | ・発注者指定型 ・施工者希望型 (発注金額、施工数量により決定) |
発注者指定型のみ |
| 加点措置 | ・起工測量から電子納品までの何れかの段階でICTを活用した工事:1点の加点 ・起工測量から電子納品までの全ての段階でICTを活用した工事:2点の加点 |
廃止 |
| 提出書類 | ① 施工計画書(使用する3次元計測機器、ソフトウェア等) ② 3次元設計データチェックシート(令和4年度から簡素化) ③ 精度確認試験結果報告書 ④ 出来形管理図表 等 |
③ 精度確認試験結果報告書の削減 ・精度確認試験結果のみの提出とする ④ 出来形管理図表の提出書類の削減 ・デジタルデータを活用し監督・検査等を実施した場合、出来形管理図表の作成・提出を不要とする |
ICT基準類の見直し
従来の出来形管理要領は1,000ページを超えており、ICT施工に挑戦しようとする人たちにとって障壁のひとつとなっていました。
国土交通省もこのことを問題視してスリム化の検討を進めており、いよいよ令和7年4月1日から新しい要領の適用が開始されます。
今回のスリム化によって重複部の共通化と構成の見直しが行われました。さらに、初めてICT施工を行う人でも容易に活用できるように「使い方ガイド」も新たに作成されています。

このほかICT活用工事の実施要領・積算要領もより受発注者に分かりやすい記載内容に見直しが行われました。
国土交通省は、基準類を活用する人たちにとって理解しやすいものとなるように工夫をしており、「難しくて分からない」は通用しなくなっていくことが分かります。
「BIM/CIM取扱要領(案)」の作成
BIM/CIM活用は「建設現場で取り扱う情報を統合管理することにより、受発注者のデータ活用・共有を容易にし、生産性を向上させること」を目的に推進されてきており、令和5年度から原則適用が始まっています。
こうした流れの中でBIM/CIMに関する基準類は数多く作成され、複雑化していました。
そこで今回、既存の基準類を整理して新しく「BIM/CIM取扱要領(案)」が作成されました。

この資料を見ると、「既存のもので新要領の内容が反映できていない箇所については、新要領の内容を優先する」とされています。
つまり、いままで既存の要領を理解・活用できていたとしても、改めて新要領の内容をよく確認し活用していくことが必要となります。
▼BIM/CIM取扱要領(案)
https://www.mlit.go.jp/tec/content/001867346.pdf
まとめ
今回は、「第13回 BIM/CIM推進委員会」と「第20回 ICT導入評議会」のなかで、わたしたちが特に注目したポイントについてまとめました。
しかし今回ご紹介したのは各会議で取り上げられた情報の一部にすぎません。
変化する建設業界で生き残っていくためには、自分が必要な情報を漏れなく確認し、それに対して適切に対応していくことが求められます。
まずはそれぞれの会議の資料に一度目を通してみてください。
また、建設ICT.comのオンラインCPDS講習でも最新情報の解説を行います。
「忙しくてなかなか資料の読み込みまでできないよ」という方がいらっしゃいましたら、ぜひ受講をご検討ください。
▼オンラインCPDS講習
https://kensetsu-ict.com/seminar/live/