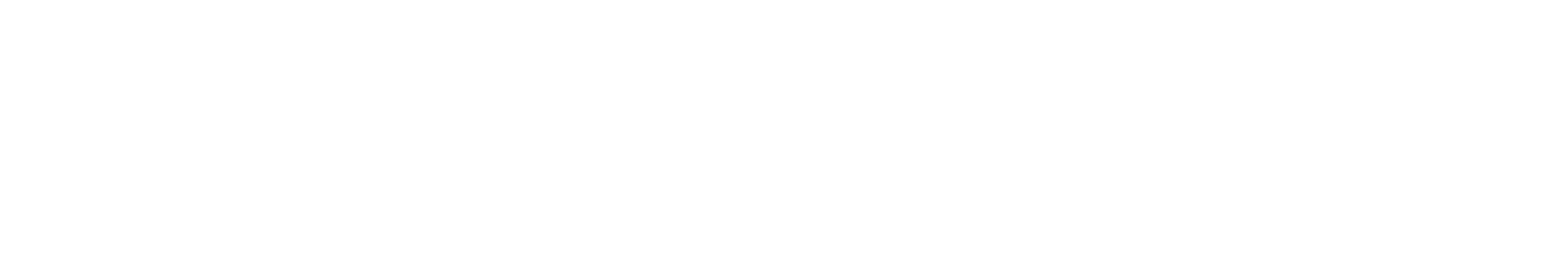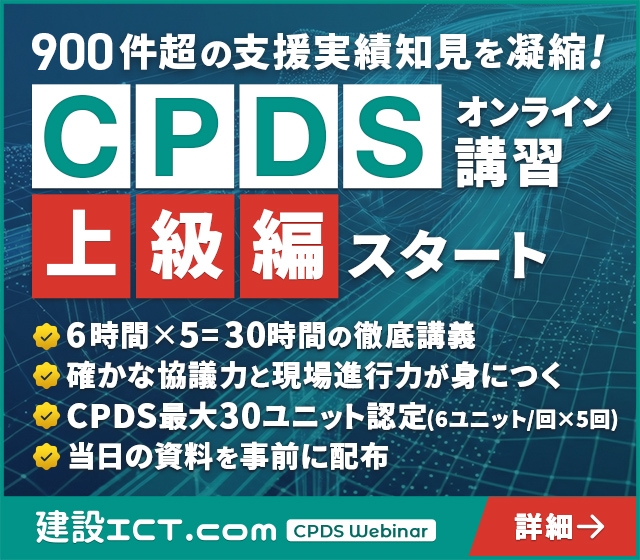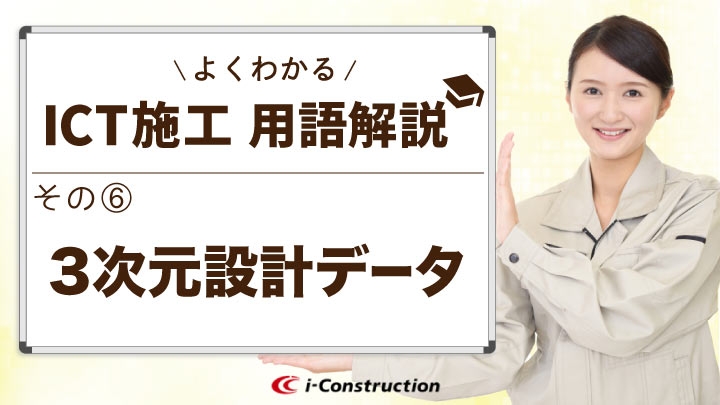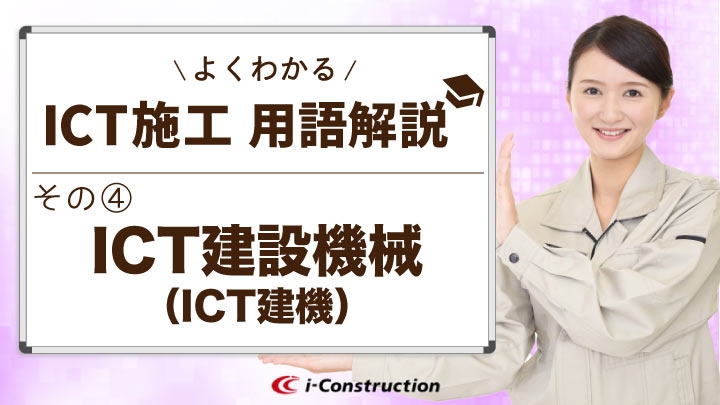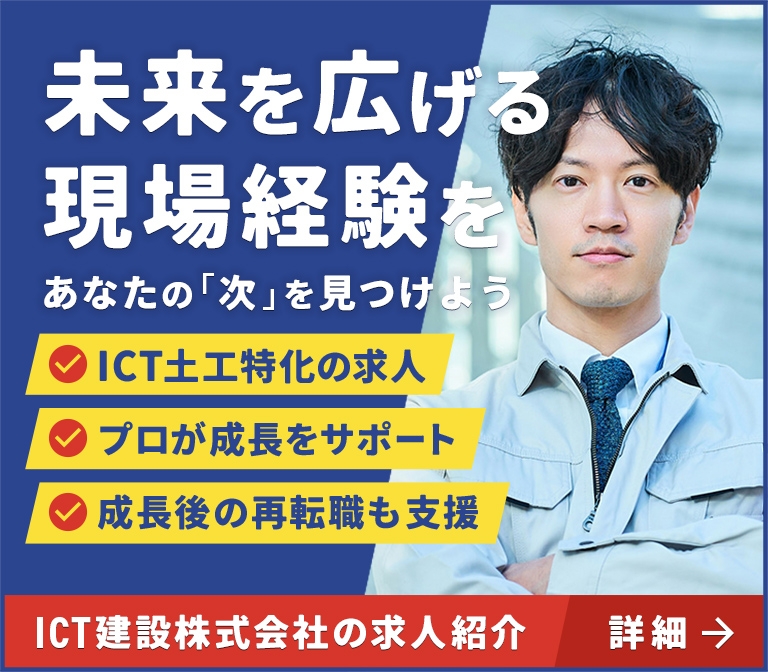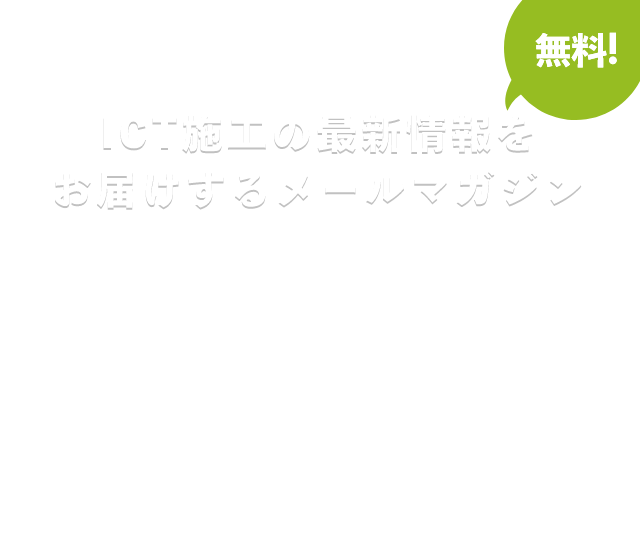はじめに
ICT施工で欠かせないもの。それが3次元設計データです。ICT施工でいう3次元設計とは、3次元化された設計図書を指します。
ICT活用工事の5つの工程(計画~測量~設計~施工~出来形管理)のおもに設計~出来形管理までで利用するとても重要なデータであり、その目的は次の2つです。
- 設計図書の照査(2次元図面と3次元図面)
- 数量算出(土量計算)
ICT施工の内製化を目指す企業様からのサポート依頼や研修要望の中で、必ず含まれると言っても良いのが3次元設計データの作成です。
今回は、総勢28名の社員様に向けた3次元設計データ作成研修【基礎編】のセミナーレポートをお届けします。
完全カスタマイズの研修
ご要望いただいたのは、すでにICT施工実績が何件もある建設会社様です。
研修の目的は、
- 社内ICT土木スキルの均一化と底上げ
- ICT施工体制強化による対応現場数のアップ
で、対象者は新人から社歴10年以上のベテランまで総勢28名でした。
3次元設計データ作成の基礎編として、ICT施工や3次元設計の知識補充と3次元CAD操作を行う実技による完全カスタマイズのカリキュラム構成による研修でした。
<3次元設計データ作成研修【基礎編】>
| 実施期間 | 10日間 |
| 実施方法 | 14名/班に分けた基礎講習(1日間) 7名/班に分けた実技講習(2日間) |
| 研修日程 | 1日目:i-Construction概要、ICT施工工程概要、3次元設計作業工程の把握 2日目:線形計算、現況横断取り込み、横断図照査、3次元設計モードによる作図 3日目:追加横断作図、土量計算、3次元設計データチェックシート作成 |
| 使用ソフトウェア | 福井コンピュータ EX-TREND武蔵 建設CAD、Trend-Point |
| 講師 | 2名 |

研修1日目【基礎知識】
研修1日目は、3次元設計データ作成の前準備として、ICT施工の基本的な概念・考え方、作業の流れ等を把握し、全員の知識レベルを均一にするために座学講習を実施しました。28名を14名ずつの2班に分け、1班あたり丸1日かけて基礎を固めました。
今回参加された方々は、入社1年目の新人作業員から、社歴10年以上のベテランや現場監督まで、社歴も役職もバラバラのメンバーでした。このようなメンバー構成でも、同じカリキュラム内容で研修を実施できるのは、i-ConstructionやICT施工が業界にとってまだまだ最新の情報や技術であり、皆がある意味同じスタートラインに立っているからだとわたしたちは考えています。
この基礎知識の座学講習は基本的な内容のため、すでにある程度理解している方が多いと予想していました。そこで、最新の国土交通省発表資料を使いながら、情報更新と知識の定着をはかることに加え、研修の目的や会社の方向性など、事前に伺ってきた幹部の方々の意向を汲み、組織として士気が高まる内容の構成にしました。
また、今回の研修は3日間という限られた時間ではありますが、できるだけ作業を繰り返すことをポイントにしていました。そのため、午後からは早速個々のPCを使った簡単な作業に入ります。この作業は、2日目以降の実技講習の流れ、CADや設計図面の用語解説を交えて、簡単な操作を一緒に行うことで、参加者のCAD操作レベルを講師が把握するという時間でもありました。


研修2日目【実技講習】
研修2日目からはPCを使った本格的な実技講習のため、7名ずつに分かれて班ごとに講習を行いました。少人数になったことで、一人一人の理解度と作業進捗を確認しながら講習を進めることができます。理解や習得度合いは人それぞれですので、作業が速い方には遅い方のフォローをお願いし、互いに協力して作業を進めることを意識していただきました。
まず、土木工事の設計で重要な線形計算を理解するところから始めます。今回の研修では、実際に施工を行ったICT現場を題材にしました。題材となった現場の線形は、一部卵形クロソイドが含まれており、一般的なテキストには書かれていない内容で多少難解です。発注図面から読み取る内容や、建設CADに入力する項目を図解しながら、何度も同じ作業を繰り返しました。線形計算は専門的な内容であるため、何となくはわかっていても、いざ作図するとなるとうまく線形が描けないなど、ベテランでも苦労されていました。
次は、Trend-Pointを使って現況横断データを作成します。3次元で表現される点群やTINデータを扱う時には、皆さんテンションが上がりますね。取り出した現況横断を建設CADに取り込み、横断図の照査、3次元設計データ作成モードによる作図へと作業を進めていきます。

研修3日目【作図作業】
3日目になると、CAD操作にも慣れ、皆さんの作業スピードと集中力がどんどん高まっているのを感じました。3次元設計データ作成で最も時間と労力を要する作業とも言える追加断面の作図に入ると、皆さんの集中力はピークを迎えます。誰一人余計な話をせず、一人一人PC画面に張り付くように作業を進める姿に大変感銘を受けました。
黙々と作図に没頭し、休憩中も席を立とうとせず、互いの進捗をあれこれと確認しあう様子から、日頃の現場作業風景を垣間見た気がしました。ゼロからものを作り上げる熱意と姿勢は、日頃の現場作業で培われたものだと思います。また、徐々に3次元形状が出来上がっていくさまを見て、純粋に楽しいと感じるのはわたしたちも含めて、3次元設計に関わるほとんどの方に共通することではないでしょうか。


まとめ
わたしたちが3次元設計データ作成の基礎講習を行う上で意識していることは、
- 3次元設計の概念やCAD操作方法、ソフトウェアの挙動を理解すること
- 平面図、縦断図、横断図からの設計要素の読み取りと3次元形状をイメージできること
です。さらに、次の段階では、
- 施工現場の状況と完成までの流れを関連付けられる知識と作図力を身に着けること
だと考えます。そのためには、日々の学習はもちろんのこと、一つでも多くのICT現場を経験することが大切です。
今回の研修では、ベテラン勢の理解の速さと効率的な作図作業に落とし込む応用力には目を見張るものがありました。これまで積み上げてきた現場経験の多さ故のことではないかと考えます。
ICTは若手がやるものと決めつけず、この建設会社様のように、新人からベテランまで積極的に学習できる環境を提供されてはいかがでしょうか。
当社では、今回の研修にように企業様のご要望に応じてセミナーや研修をカスタマイズしてご提供することができます。3次元設計データ作成以外の工程に関する内容でも結構ですので、ご希望の際はお気軽にお問合せください。