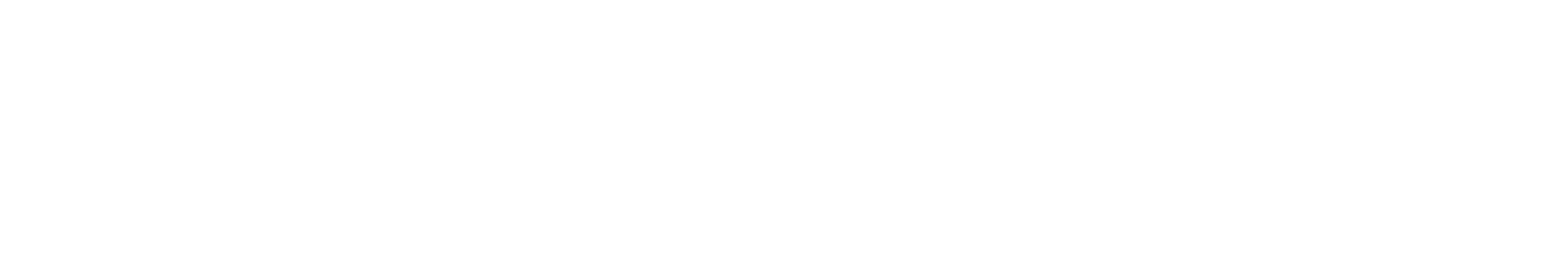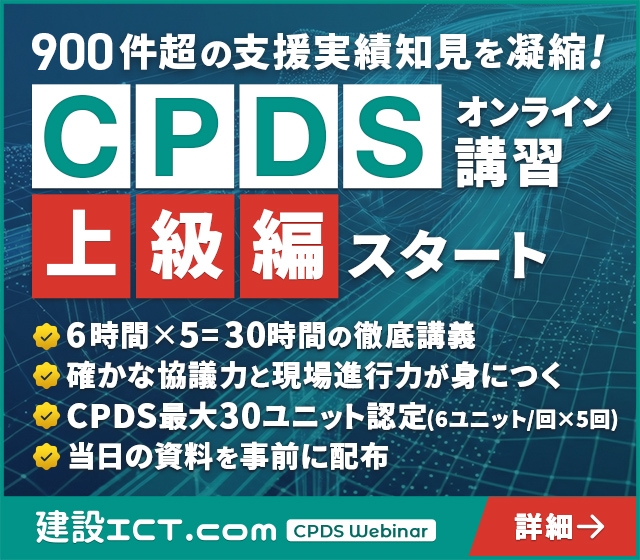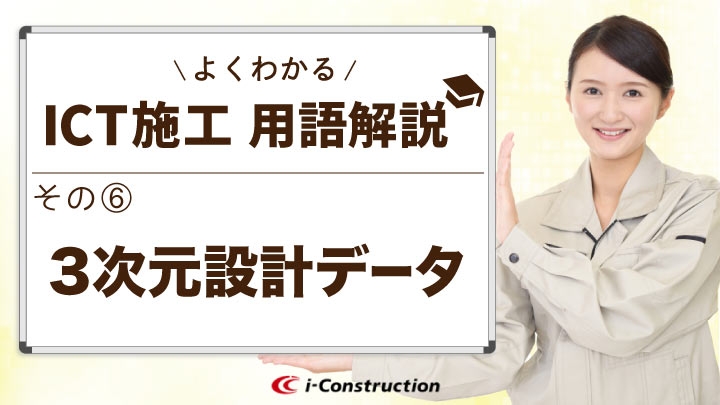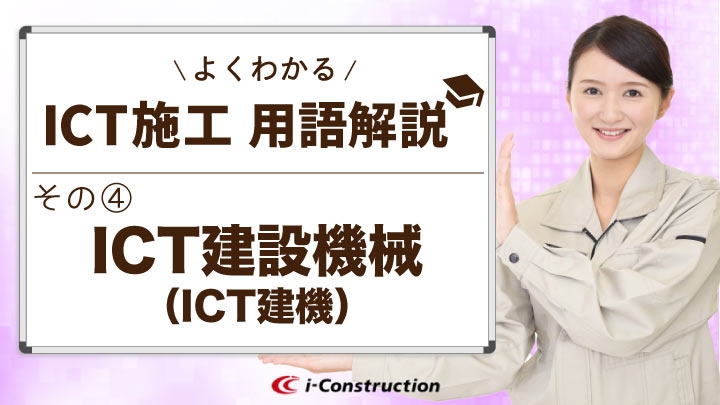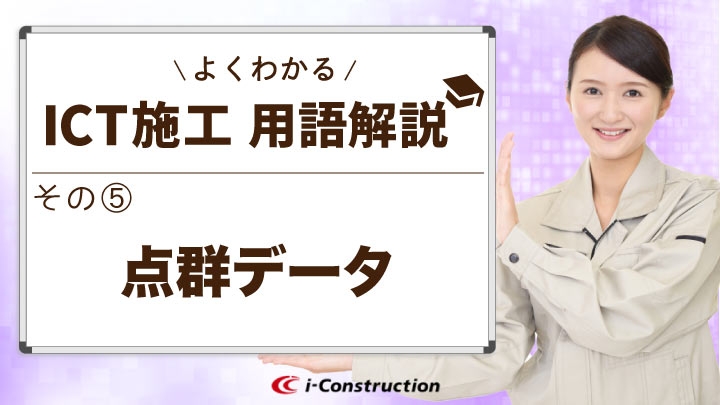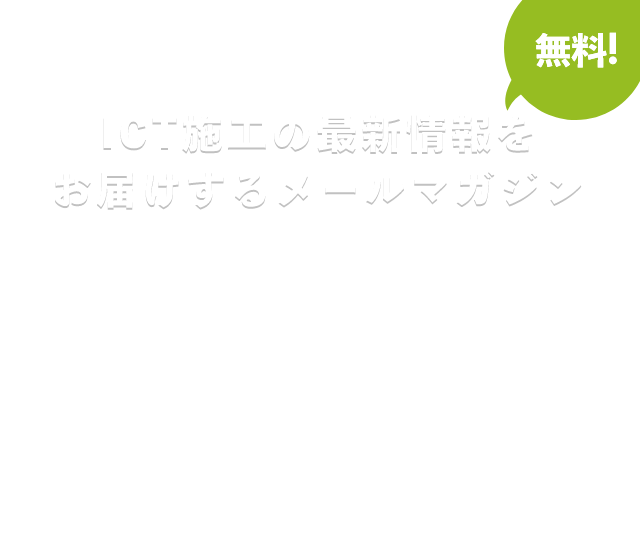はじめに
今回は、ICT土木工事の現場で闘う建設業界の皆様、i-Constructionの取り組みに尽力される行政機関の皆様に向けて、経営コンサルティング会社であり、測量会社でもある私たちが、数々のICT土木現場経験から得た知見から、独自の視点でICT土木工事成功の鍵についてお伝えしたいと思います。
まずは自社で内製化できることが大切
ICT土木現場における実務サポートや主催するセミナーの場では、必ず次のことをお伝えしています。
「ICT土木工事は、まず自社で内製化できる状態になることが大切」
ICT施工を実施する上で利益化を目指すためには、自社内で各工程を内製化できる状態になっておくことが大切です。内製化できるということは、各工程の知識を得ているということですので、効率化を図るために一部の作業を外注した場合にも、その知識を有効活用することができます。詳しくは、以前の記事で開設しておりますのでご参考ください。
コラム「利益を生み出すICT施工の実現には何が必要なのか!?ずばりお答えします」
どの工事においても、たった1社だけで発注から納品・検査までを完結させることは不可能でしょう。まず、発注元の業者がなければ工事を受注することも無いわけですから、そこには必ず、自社以外の業者との関係が生じてきます。
ICT土木工事に関わる会社の関係図
ここで、土木工事に関わる業者の関係性を、公共工事を例に整理しておきたいと思います。
- 発注者(行政)と受注者(建設会社)
- 元請業者と下請業者(一次・二次…)
<その他関係業者>
資材業者、運搬業者、警備業者、リース業者、測量業者など
今回の記事でお伝えしたい内容では、施工体制台帳の構成は考慮せず、ICT施工の5つの工程(※)に関わる主な関係業者に注目して整理することにします。
- 3次元起工測量
- 3次元設計データの作成
- ICT建機による施工
- 3次元出来形計測
- 3次元データ納品
それぞれの関係性を元請業者の建設会社を中心にまとめてみます。

契約形態によっては相関関係が違うこともあると思いますが、あくまでも関わる業者を一例としてイメージしていただければと思います。
〇と〇な関係がベスト
ICT施工の各工程を、自社で内製化することが重要なのは前述の通りです。内製化できる状態でありながら、会社全体でより効率的なICT土木工事を進めていく場合、あえて一部作業を外注するという選択をされる建設会社様もいらっしゃいます。その時、ICT施工の知識をコンプリート(内製化)した元請業者が外注業者に求めるものは何でしょうか。
それは、元請業者と同等レベルの知識があるかどうかということです。そのレベルに達しているとなると、次のような効果が生まれます。
- 共通認識を持つことで同じゴール(方向)に向かうことができる
- 共通言語を持つことでコミュニケーションが円滑になる
- 共通理解ができることで工事の安全性・品質・効率が上がる
このような効果を生み出せる関係性であることを、わたしたちはシンプルに「〇(まる)と〇(まる)な関係」と表現しています。この関係性を持つことがICT土木工事の成功の鍵になるのです。

ちなみに、この〇と〇な関係は発注者と受注者の関係でも同じであることは言うまでもありません。
まとめ
ICT土木工事の成功の鍵は、すべての工程において関わる業者が「〇と〇な関係」であることです。
この関係性を持った業者同士がICT土木工事に取り組み、成功を重ねていくと、関係性はより強化されていきます。ただし、そのためには双方の知識・経験の蓄積と、新たな情報の更新、次のステップへの進化が必要になります。その努力を怠らないことが、〇と〇な関係性を継続させる秘訣となるでしょう。これは、業界や企業であることを問わず、人間関係にも言えることですね。
建設ICT.comでは、サイト運営会社であるストラテジクスマネジメントのコンサルティングノウハウ、測量会社としてのサポート実績をもとに、今後もICT土木工事の内製化を目指す建設会社様、i-Construction取り組みを推進される行政機関の皆様に、お役に立つ情報をどんどん発信していきます。
また、内製化に向けて取り組むべき具体的内容など、詳細情報の提供をご希望の企業様はお気軽にお問合せください。担当よりご説明いたします。